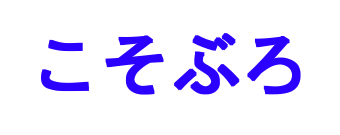switch用ニンテンーウライセンスのタタコンを自分の手で改造・修理してみました。
結果、半分成功、半分失敗したので、詳細を書いていきます。
*タタコン改造は完全に自己責任の範疇です!!ちなみに分解済みのタタコンは、メーカー保証対象外になってしまうのでご注意を!!
タタコン改造とは

タタコンの改造とは、より良いタタコンの精度を求めて、改良することです。
主に、「ドン」部分は木材をはめ込み、「カン」部分はゴムを貼ることによってセンサーの精度などを高めることが出来るらしいです。
我が家のタタコンは、「ドン=良反応」です。正直改造とかいらないでしょ?ってくらいいい反応です。
一方、「カン=イマイチ反応」なのです…。具体的に言うと、左枠を叩くとたまに反応しません…。音が抜けます。
全く反応しない訳じゃないし、多分修理・交換をお願いする程の不良じゃないんですよね~…。
こっちはもう、改造というより修理の範疇かも…。
さて、より良い反応を求めてやって見ましょう!
材料の用意
材料は以下です。
- 木の板(今回は厚保さ9mmを使用)
- 平ゴム
- 両面テープ
この他に木の板を切るノコギリと、ネジを外すための+ドライバーを使います。
後で出てきますが、木の板の厚さが難しいです。
実は9mmで失敗しています…。
平ゴムとは、平たい太い輪ゴムです。本来はゴム版(?)を使う方が多いようですね。
100均でそれらしきものを探したのですが、見つからなかったので代用として平ゴムにしました。
両面テープはいたって普通のものです。平ゴムを貼る時に使います。
分解と改造
分解する
タタコンの台座を取り外して、裏のネジ5つをドライバーで外します。
この時、基本ですが、ネジを無くさないように注意します。

ネジを外すと赤い部分がパカっと取れます。
すると中には基盤とコードがあります。
下写真の基盤の右一つ(灰色のコード)と、左三つ(黒緑のコード)を取り外します。
取り外し方はシンプルで、コードの先端の白い部分を引っ張れば取れます。
ただ、かなり固い!!ほんとに固い!基盤がバキッと壊れるんじゃと思うくらい固かったです。
ちなみに後で気付いたのですが、改造のやり方によってはこのコードは外さなくてもOKです。
「ドン」のセンサーを剥がして改造する場合はコードを外さないと難しいけど、「カン」の部分だけや、「ドン」のセンサーを剥がさない改造なら、別にコードを外さなくても出来ます。
基盤部分とコードを触るのは不安という人は、そのほうがいいかもしれません。

コードと基盤を外すと、面部分を完全に取り外せます。
ここから先は面部分の分解になります。

まず面部分の土台とラバーを分けます。
ラバーの突起が15か所くらい土台にはめてあるので、それを外せばいいのですが、すごく固いです。
手が痛くなります…。汗で滑ってしまう場合には、ゴム手袋などをして外すとやりやすいです。
ラバーが外せたら分解は終了です!
改造する
分解出来たら、面土台に入っている黒いスポンジを取り出します。
そして、木の板を黒いスポンジと同じ形に切ります。
この時、全く同じサイズではなくて、少し小さめに切ったほうがその後の作業がやりやすいです。
あまりピッタリや大きめのサイズだと、うまくはまってくれないからです。

次に面土台に入っているドンのセンサーを、プラスチックの板からはがし、
代わりに、先ほど作った木の板に両面テープで貼り付けました。
センサーを剥がす時は「壊れないかな?」とドキドキしますが、案外頑丈で、ゆっくり丁寧に剥がせば大丈夫です。
以下の写真は剥がしている途中の図です。

最後にカン部分です。
平ゴムを適度なサイズに切り、両面テープを使って、写真のように「カン」センサーに貼り付けます。
この時、センサー全体を覆うように貼ると、うまくいかないらしいので少しずらして貼りました。

後は解体と反対の手順で組み立てて完成です!!
改造・修理結果と手直し
結果、失敗しました。
「カン」はOKだったのですが、「ドン」の部分で使った板の厚みが足りなかったらしく、叩くとベコベコと凹んでしまいました。ドンセンサー+9㎜の板だと薄すぎるようです。
反応しないわけではないけど、これなら改造前の方が明らかに優秀・・・。
そこで手直し1回目です。ドンセンサーを元のプラスチック板に張り直し、黒スポンジと木の板を入れ替えることにしました。ドンセンサー+プラ板+9mm木の板の組あわせです。
結果2、失敗しました。
「ドン」はいい感じになったのですが、今度は「カン」の入力が入りっぱなしになってしまいました。
さっきは「カン」はOKだったので、「ドン」の手直しが何か影響したのでしょう。
「カン」が入りっぱなしとかありえません。手直し2回目です。
「ドン」はもともと感度が良かったので、今回は改造することを諦め、ドンセンサー+プラ板+黒スポンジという最初の仕様に戻しました。
頑張って木の板切ったのに、無駄になってしまいまいましたね。
一方、「カン」は元の感度に不安があったので、何とか良くしたい・・・。
そこで平ゴムは採用です。
結果3、成功(?)です。
「ドン」は最初と同じ感度ですが、「カン」の方は劇的に良くなりました!
本当に違います。抜けることがなくなりました!!
どのくらい違うかというと、「カン」の反応の改善という1つの変化だけで、
今までクリアできなかった鬼レベルの曲が余裕でクリアできました!!
まとめ
結果的に「カン」は成功、「ドン」は失敗に終わりました。
「カン」だけなら、頑張って基盤とコードを外さなくてもよかったのに。
基盤もしくはコードの差し込み部分がバキッと壊れそうで正直かなり怖かったんです。
でもまぁ、自己流の改造・修理は失敗と改良の繰り返しなので、それも必要な過程だったかな…。
おかげで、「何とか鬼レベルをクリアできるタタコン」から「余裕で鬼レベルをクリアできるタタコン」へと進化しました!
いや~途中でタタコン壊さなくてよかった!!