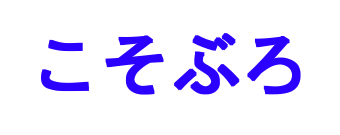ラズベリーを3種類育てています。
インディアンサマー・グレンモイ・グレンアンプルです。
一番長く育てているインディアンサマー1季目収穫となったので、様子を書いていきます。
インディアンサマー
- トゲ有
- 2季なり
- ホームセンターに売っている
最初に買ったラズベリーです。
ホームセンターにも良く売っているので、入手しやすいです。
2季なりで、6月&11月に収穫できます。
ただし、6月は梅雨の時期に当たってしまい病気や腐りが出ます。
また、秋も年によっては秋雨とぶつかり、実が痛みます。
5月 開花
5月に入ると次々と開花してきます。
小さな白い花で、目立ちませんし特別綺麗ではありません。
しかし、この花が赤い実になるのだから大事にしないと!
花は昨年伸びた枝&新しく地面から伸びた枝先の両方につきます。
なので私は、冬の剪定の時、太い枝だけフェンスに誘引しておきます。
別に全部切ってしまって、新しい枝のみに結実させてもいいのですが…。
それだと収穫量が減ちゃうので。

地面近くが新しい枝です。
ちょこちょこ花&実がついていますね!
茶色い枝が見える上の方が、一冬越した部分です。
沢山の花&実が見えます。
やはり去年の枝を残した方が、1回目の収穫量が期待できます。
6月 1季目収穫
株の様子
6月に入るとだんだん実が赤くなってきます。
薄い赤はまだ未熟なので、食べても美味しくありません。
真っ赤になったものじゃないと!
しかしこの収穫のタイミングが厄介で…
真っ赤になってから1~2日ですぐダメになってしまいます。
おまけに一斉に赤くなることはなく、毎日数個ずつ赤くなります。
なので毎日チェックと収穫をしなければなりません。
今は学校帰りの子供と一緒に楽しく収穫してるけど、そのうち面倒くさくなりそうな予感がします…。

去年からある古枝の方は、この時期なると勢いが落ちてきます。
葉も少し黄色くなっているのがわかりやすいですね。
一方、地面近くの葉は奇麗な緑色ですし、太いシュートも出ています。
秋の実はこっちの枝に着きます。
実の様子
6月の実はこんな感じです。
1~2㎝と、サイズはまちまちです。
特別大きい! っていう実はないかな…全体的に小粒ですね。


味は、収穫のタイミングによります(笑)
真っ赤になったものは美味しいけど、それ以外そんなに美味しくない…。
種の触感が結構あるので、それも難点の一つでしょうか。
また、小さな虫が付いていることが多いので、塩水かお湯につけて洗うのが必須です。
ちなみに我が家、ジャムにすることが多いです。
収穫したものを順次冷凍し、全部収穫し終わったら一斉にジャムにします。
色見も綺麗で甘酸っぱくてとても美味しいです!
梅雨対策
1季目の収穫は、梅雨にドンピシャで重なります!
ラズベリーは物凄く雨に弱いので、ちゃんと収穫したいなら雨よけ必須です。
わが家では雨の日だけ園芸用ビニールを掛け、洗濯ばさみでとめています。
かなり適当ですが、我が家はとりあえずこれで充分。
このように適当な雨除けですが、これだけでかなり良い実が沢山収穫できるようになります。
そうしないと、とてもじゃないけど食べられない。
一部が痛んでいたり、カビていたり…。
梅雨の中晴れに期待するのもアリですが、雨よけしたほうが確実ですね。
実がなった枝の剪定
6月最終週になると、もう実がダメになってきます。
何でしょう? 暑すぎるのかな? こんな感じで熟す前に腐ります。
なので、こうなったらもう収穫は終了です。

さて! 剪定作業です!
まず、去年からある古い枝は根元から全部撤去します。
沢山実を付けてくれてありがとう!
春に新しく伸びてきた、地面近くの枝ですが…。
基本的には実を付けた枝は根元から切ってしまいます。
実を付けた先端だけ切って、他を残してもいいけど…それだと混みあってしまうんですよね。
勢いのある新梢が沢山あるので、そっちを残して他を切ります。
風通し、大事!
バンバン切っていると…虫に遭遇しました…。
木くず&穴、そしてちょうどハサミを入れた個所にテッポウムシらしきもの…!
いや~実が痛んできたのって、もしかしてこれのせいだったかも?

虫はさておき、どんどん切ってこんなにスッキリしました。
残った枝には2季目の実がなります。
楽しみ!

感想
インディアンサマー、かなり育てやすいです。
初夏と秋の2回収穫出来るのも良いですね。
今回1季目の収穫をしましたが、雨よけのおかげで9割くらいをちゃんと取れました。
残り1割は腐っていたり、痛んでいたり…まぁこのくらいは仕方ないですけどね…。
味は、良く熟したものは生食が良いです。
でもちょっと早くとってしまうこともしばしば…そういうのはジャムにすると大変美味しいです♪
ちなみに秋はもっと良い実が出来ます。
たのしみだな~♪
果樹栽培の記録はこちら! 果樹 | こそぶろ (kosoburo.com)